~幸田露伴 原作 “二宮尊徳翁”を読む(その2)生まれながらの偉人はいない~
◎【あらすじ】経済的に厳しい家庭環境で育つ(前回の続き)
二宮尊徳先生は、天明7年(1787年)7月23日、相模国の栢山(かやま)村(現・小田原市)に生まれました。比較的裕福な家庭に生まれましたが、様々な要因が重なり、二宮家は没落してしまいました。
尊徳先生が、生まれながらの才能ではなく、努力の積み重ねで人生の逆境を克服していく、地に足のついた成功の物語がここに始まります。
原文:二宮先生とて生まれながらに君子にても豪傑にてもあらざりしなり、先生は天明7年7月23日、相模の国の柏山村といへる片田舎に生まれ玉へり、家は貧しきが上に酒匂川の洪水先生の5歳の時1畝も残さず先生が家の田圃を荒らしければ、いよいよ貧しきを重ねて先生と先生の弟三郎左衛門富次郎の二人とを育つることさへ容易からぬほどなりけるが
現代語訳:二宮先生は、生まれながらにして立派な人物だったわけではありません。先生は天明7年7月23日、相模国柏山村という田舎に生まれました。家は貧しく、先生が5歳の時に酒匂川の洪水で田んぼがすべて流されてしまい、さらに貧しさが重なりました。弟の三郎左衛門と富次郎を育てることさえも難しいほどの状況でした。
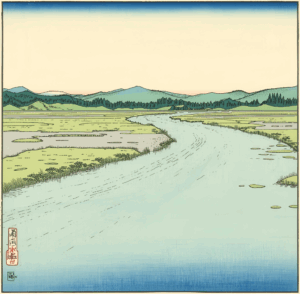
酒匂川。浮世絵風の
イメージ画像です。

立ちすくむ二宮親子のイメージ画像です。
おぜき重太郎のコメント:この話にもあるように「生まれながらの偉人は」いません。尊徳先生は、貧しさや災害という厳しい現実の中で育ち、家族を思い努力を重ねることで、立派な人物へと成長しました。鎌倉時代から明治時代の中期まで使われていた初等教科書『童子教』には、「生まれながらにして貴き(たっとき)者は無し。習い修めて智徳(ちとく)を成す」とあります。物事が上手くいかなくても自分の境遇に不満を持たず、真摯に努力を積み重ねることが、自分の運命を変える秘訣だと教えているのです。
(議会レポート2025年6月号(広域版)より 執筆者:おぜき重太郎)

