町田市立 自由民権資料館 の “町田の歴史” 展を見る
町田市には 約3万年の歴史があります。以前、里山の歴史について少し触れましたが、町田市立「自由民権資料館」では “町田の歴史” 展が開催されているので、今回は、町田市3万年の歴史を、実物資料とともに、通史的に知ることができる展示についてご紹介いたします。
展示会のキーワードは“くらし” です。昔の人が使った身近な道具や資料を見ながら自分たちが住んでいる地域に、どんな人々が暮らしていたのか学んでみるのはいかがでしょうか。新たな発見とともに町田への愛着が増していくこと請け合いです。
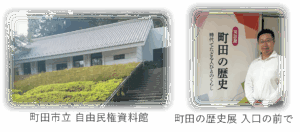
見れば納得! “町田の歴史”展 の見どころは?
町田の歴史 ~時代でたどる人びとのくらし~展では、旧石器時代から昭和時代まで、さまざまな展示がなされています。私の取材中にも家族の訪問客があり「こんなものが町田であるんだ」と感嘆の声も聞こえてきました。
【参考】私が感じた各時代の見どころ
旧石器時代:木曽森野遺跡で発見された約3万年前の石刃(写真)を見ながら、町田の始まりを感じました。
縄文時代:町田のストーンサークル(田端環状積石遺構)の資料やクルミ形の土器の実物、子どもたちに大人気の中空土偶の頭部(愛称“まっくぅ”)のレプリカを見ながら、ドングリやクルミ、シカやイノシシなどを食べていた、昔の採取・狩猟生活を頭に思い描きました。
弥生時代:出土した土器や集落(遺跡)の数が少なくなります。水田稲作が伝わるも、町田の丘陵地には適さず、適地に移住してしまったようです。
古墳時代:西谷戸横穴墓群から出土した刀の金具など金色の副葬品を見て、金銅が使われ技術が進歩していることを感じました。
奈良時代:瓦の破片(写真)を見ながら、ブラタモリで相原・小山の窯跡群が紹介されていたことを思い出しました。瓦や土器を通じて近隣地域と交流や流通をしていたことに思いを寄せました。
平安時代:木曽中学校付近で発見された忠生遺跡では、竪穴住居が60棟、掘立柱住居が40棟もの跡が見つかり、その集落の大きさに驚きました。
室町時代:能ヶ谷で発見された銭貨9万枚の写真や渡来銭の現物からは当時からお金が貴重品であることが伺えました。また、逃げた農民に帰村と1年間の年貢免除を命ずる北条氏照朱印状などを見て年貢の重さを感じ取りました。
江戸時代:当時、町田には27の村があったそうです。当時の絵図を見ると、野津田村は畑作が広がり薬師池があるため水田があったようです。また、相原村の質物出入帳からは、八王子からも質入れに来ていた様子が伺えて、貨幣経済の浸透を感じました。
幕末~明治維新:旧家に残された瓦版からは、横浜の開国をいち早くキャッチしていた様子が伺えました。また、明治新政府の高札や小野路村の農兵隊の装備を見て、幕府が倒れ新政府が誕生した不安定な時代を、懸命に生き抜こうとする町田の民衆の姿を感じることができました。
明治時代:町田市内は、合併により5つの村が誕生しています。現在の学校制度の元となる学制が発布され小学校がたくさんつくられたことや、戸籍制度と同時に徴兵制度も整備され、町田の民衆が出兵するという明治近代国家の光と影の部分を見ました。
昭和時代:B29のプロペラ(写真)など戦争の時代を偲びつつ、戦後は町村合併のよって今の町田市が誕生、商業都市として発展していく激動・激変の時代を感じました。

子どもたちに大人気! “まっくう”を応援しよう
なお、町田の歴史展でレプリカが展示されている、中空土偶の頭部ですが、“まっくう”という愛称で町田の子どもたちに親しまれています。町田市は、まちだ縄文キャラクター「まっくう」を商標登録しており、美術館系のキャラクター・コンテストである「ミュージアム・キャラクター・アワード」にエントリーするなど町田市のPRに活用しています。

おぜき重太郎のコメント:この他にも、町田の歴史に興味を持っていただく取り組みとして町田市の小学校では、年間20~30校に“まっくう給食”(まっくうトーストやまっくうのり)が提供されています。応援したい取り組みですね!
(町声レポート2025年5月号より 執筆者:おぜき重太郎)

